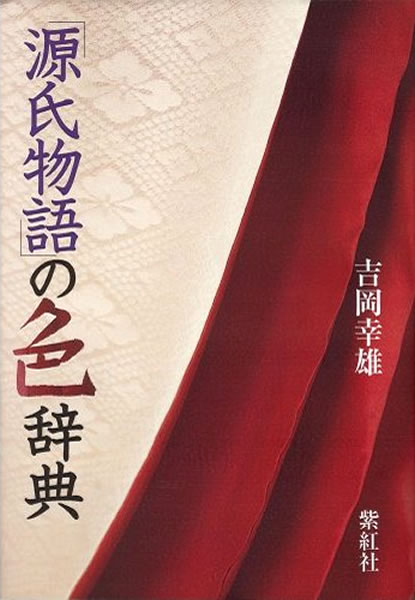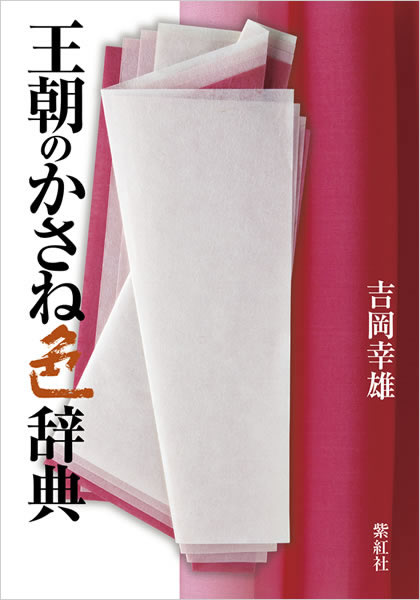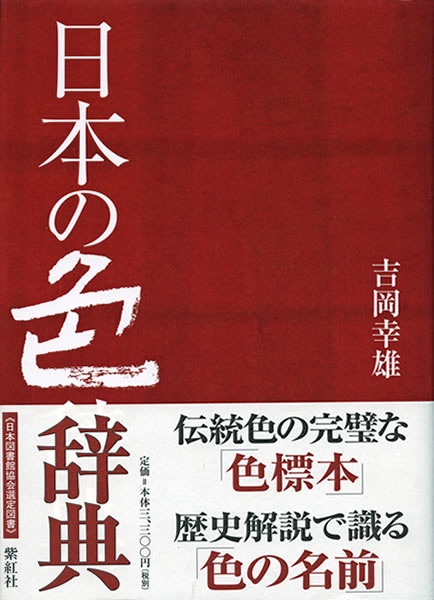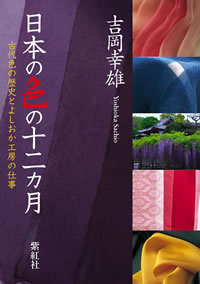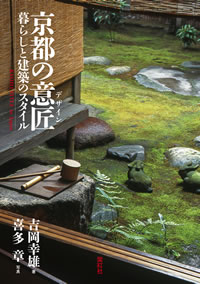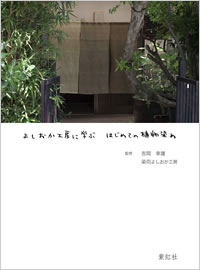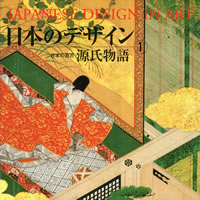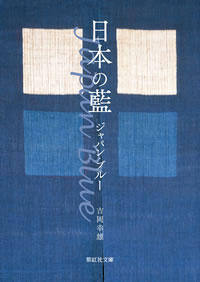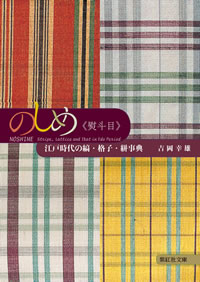「染司よしおか」五代目当主・吉岡幸雄氏が選んだ今月の色の過去の記事より、人気のエッセイを紹介しています。
2010年5月
「紫のゆかり」ふたたび

今年はどうも気候が不順で、なかなか春らしい日が続かない。
四月の終わりから五月の始めは、二十四節気では「穀雨」ということになっていて、これからの田植えや、夏の野菜の苗を畑に移すようなときに、恵みの雨を与えてくれるというころである。ところが、四月も二十日を過ぎても、関東や北国のほうでは雪やアラレが舞った。
そして今年は五月五日が「立夏」、まさしく夏をむかえるという感じのつかめる時期なのである。はたして、四月の気候を見ていると順調に巡ってきてくれるか、心許なくなる。
私は、かってに五月の頃は、初夏を迎える日々を紫の彩りの季 (とき) と呼んでいる。
まず藤の花が咲く。宇治の平等院の阿弥陀池のそばの棚には、藤の花が垂れて風にゆっくりとゆれている。西山、大原野神社は少しおくれて美しく咲く。いずれも王朝貴族藤原氏ゆかりの場所である。
五月一五日の葵祭がおわると、上賀茂神社の近く、その末社になる太田神社の沢には、杜若 (かきつばた) の濃き紫の花が咲く。そして、上賀茂神社の競べ馬が行われる馬場の近くには桐の花が咲く。
このような紫の花の巡りのことは、私の定番で、いつもどこにでも書いているので、いささか面はゆい。
こうした紫の彩りをかもし出す染料としては古くから紫草という草の根が使われてきた。京都近郊ではその紫草を観賞するのは難しいが、初夏に白い小さな花を咲かせる。緑の葉のうえに可憐な花を咲かせるのだが、表からは紫の色は全く見えないのである。多年草の宿根で、根にその色素が含まれているのである。
例えば九州の阿蘇山の周辺、大分県竹田市辺りや、富士山の東側甲府、そして東京都の日野、吉祥寺三鷹といった武蔵野あたりにかつては多く自生していたとされている。つまりは、火山灰の土がその生育に適していたと考えられるのである。
紫草は強靱な植物ではなく、環境が悪くなると、その生育に影響を及ぼすらしく野生のものはだんだんと少なくなっている。だが、大分県竹田市、島根県の雲南市、京都府の福知山市など紫草を愛する方々が、復活させるべく、栽培に力を注がれていて、復活の兆しがあることは、喜ばしいことである。
「源氏物語」はまさしく紫の彩りの物語といってよく、一昨年の「源氏物語千年紀」は、「紫のゆかりふたたび」というキャッチフレーズが付けられたことをご記憶の方も多いかと思う。
私のような植物染屋にとっては、この紫の季 (とき) に、そのフレーズのように、日本に紫草がふたたび甦ってくれることを願うのである。
「藤の花」デスクトップ壁紙無料ダウンロード

お使いの画面の解像度に合ったサイズをお選びください。
日本の伝統色 ミニ知識